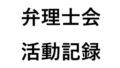先行技術調査は特許調査のなかで最もポピュラーな調査の1つです。先行技術調査を行うことで、自社の発明品についてより高い確率で特許を取得できるようになります。また、他社の特許出願状況を見て、特許出願を中止してコストを他の事に回したり、自社製品に対する新たな着想を得たりすることもできます。本稿では、その特許出願に関するメリットやデメリットについて紹介します。
先行技術調査とは
先行技術調査とは、自分たちの発明(調査対象)と同じ発明又はそれに最も近い発明が他社によって特許出願等されていないかを特許出願前に探索する調査です。調査対象と同じ又は最も近い発明を見つけるために、調査対象に最も近い発明が含まれると考えられる検索式を作成し、検索式から得られた特許文献を検討します。検討にかけられるコストには限りがありますので、検索結果の特許文献数はあまり多くしないことが望ましく、概ね100~200件程度の特許文献が含まれる検索式を作成することが多いと思われます。
先行技術調査のメリット
先行技術調査のメリットとして考えられることは次の通りです。
権利化可能性を高めることができる
先行技術調査のメリットの1つは、特許出願後に特許権利化の可能性を高められることです。先行技術調査によって、自分たちの発明に最も近い特許文献が見つかった場合、その特許文献から差別化した内容を特許明細書に記載できます。予め見つかった特許文献から差別化した内容を明細書に記載しておくことで、特許出願を諦めるのではなく、権利化の可能性を高めることができます。
効率的な特許出願が可能
先行技術調査の他のメリットの1つに、効率的な特許出願が可能になるということがあります。調査で見つかった特許文献から差別化した内容を記載しておけば、権利化の可能性を高めることはできるものの、その記載した内容によっては、権利化しても意味が特許になる可能性もあります。そのような場合には、調査結果を踏まえて特許出願を断念することもできます。特許出願から審査請求までに係る費用は大体50~60万円です。その費用が1回先行技術調査をするだけで無駄にならなくて済みます。
技術動向を把握可能
先行技術調査によって得られた特許文献を見ることで、競合他社や自社が開発しようとしている技術動向を把握できます。技術動向が把握できれば、他社と重複した技術開発することを防止したり、特許文献を参考にして他社よりも優れた技術を開発することができます。
先行技術調査のデメリット
ここまで先行技術調査のメリットを紹介してきました。次に先行技術調査のデメリットを紹介します。
出願とは別にコストが発生する
先行技術調査では、特許出願とは別にお金や時間等のコストが発生します。先行技術調査を社内で行う場合、従業員の時間が必要になります。一方、特許事務所等に先行技術調査を依頼した場合、特許事務所に支払うお金が必要になります。先行技術調査にどれくらいのコストを支払うかは、会社次第ですが、時間にしたら0.5~1営業日程度、お金にしたら5~10万円程度が妥当ではないかと思います。それ以上のコストが見込まれるようであれば、個々の技術に対する先行技術調査は行わずに他の知財業務(技術動向調査、侵害予防調査等)にコストをかけることも考えられると思います。
特許文献を読まなければならない
先行技術調査では特許文献を抽出後にそれらを読み込むことが必要になります(当たり前のことですが…)。しかし、特許文献の読み込みは、慣れない人にとっては大きな負担になります。先行技術調査では概ね100~200件程度の特許文献を読むことになると思いますが、これらの要約書(200~400字程度)を読んでスクリーニングするだけでも、結構な時間がかかります。仮に、1件1分でスクリーニングしても2~3時間程度かかります。スクリーニングで残った文献は、より詳細に読み込むことになりますので、さらに時間がかかります。
まとめ
以上が先行技術調査のメリットとデメリットになります。先行技術調査を行うことで、特許の権利化可能性を高めることができ、効率的な特許出願が可能になります。また、他社の特許出願を見ることができますので、その技術分野や競合他社の技術動向を知ることができます。一方で、先行技術調査は特許出願とは別にコストが発生したり、抽出した特許文献を読まなければならないといったデメリットも存在します。